 |
|
| 会社代表ご挨拶 | 会社概要 | リンク | サイトマップ | お問合せ | |
| H O M E |
|
|
|
|
|
食と健康の話題
細菌による食中毒の話
食品製造のための衛生講座
技術士(農業)星野 正美/平成13年6月29日
伝染病と食中毒
| 1) |
伝染病は人から人へ直接伝染する。菌数が少なくても伝染して発病する。 |
|
|
| 2) |
食中毒は原則として人から人への伝染はない。菌数が多くなければ発病しない。食してから短時間で発病する。早ければ30分、ほとんどが1日以内に発病。しかし中には2~3日間の潜伏期間後発病の場合もある。 |
食中毒原因菌
各食中毒菌による食中毒の特徴と我国での発生状況
| ① サルモネラ菌 (Salmonella enterica) |
|
この菌が多量についた食品を摂ると、潜伏期間
(多くは食後12~36時間、場合によっては2~3日間)
後、急激に発熱し、40℃にも達することがある。一般的症状としては、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱および頭痛である。
この菌はなんら病的症状のない、鳥類、動物の腸内に存在することも多い。家畜やペット、さらには人がサルモネラ菌に感染している場合もある。それらの糞に由来する菌により食品が汚染される機会も多い。調査では検査した鶏肉や畜肉の20%が、問題にならない程度の少ない菌数ではあるが、サルモネラ菌に汚染されていたそうであり、これらの食肉を長時間室温など温度の高い場所に放置すると、菌が増えて中毒の危険が生じる。
この菌は熱に弱いので加熱処理によりこの食中毒は免れる。また酸や食塩にも弱いので、加工食品では適切な食酢あるいは食塩の添加、またはこの併用でこの危険から逃れることができる。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
350 |
16,576 |
3 |
| 平成 9年 |
521 |
10,926 |
2 |
| 平成10年 |
757 |
11,471 |
1 |
| 平成11年 |
825 |
11,888 |
3 |
| 平成12年 |
512 |
6,903 |
1 |
| ② 腸炎ビブリオ菌 (non-O1 Vibrio cholerae) |
|
この菌が多量に付いた食品を摂ると、潜伏期間
(3時間~3日、多くは12~24時間)
後、吐き気、嘔吐、発熱、頭痛、腹痛、水様状態の便の下痢などの症状を起こす。時として、赤痢のように粘液便や血便症状を起こす。
この菌は夏の温度と食塩が好きでかつて好塩ビブリオと呼ばれていた。海水など塩分の高い水中でも繁殖する。しかし低温では増殖せず冬の海水からは検出されない。世界中の海に存在しているので暖かい海で取れるものはすべてこの菌で汚染されているわけである。従って、海水温の高い時期に捕獲された魚介類は、すべて腸炎ビブリオに汚染されており、漁獲後の取り扱いおよび調理、加工で菌を増やすことのないよう注意すべきである。高温下での増殖速度は極めて速く、37℃では汚染後90分で、発病可能菌数に達する。
この菌は熱と酸に弱いので、熱処理や食酢などの処理により殺菌できるが大量に菌が生育すると生産された耐熱性の毒素が残るので注意が必要である。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
292 |
5,241 |
0 |
| 平成 9年 |
568 |
6,786 |
0 |
| 平成10年 |
839 |
12,318 |
0 |
| 平成11年 |
667 |
9,396 |
1 |
| 平成12年 |
416 |
3,593 |
0 |
| ③ ウェルシュ菌 (Clostridium perfringens) |
|
この菌が多量に増殖した食品を取ると、8時間から24時間の潜伏期の後に、腹痛、吐き気、下痢をともなって発病する。
この菌は自然界 (土壌や糞埃) に広く分布し、病的症状のない健康な人や動物の腸内にもかなりの確率
(15%くらい) で存在する。空気 (酸素)
が苦手なため自然界では胞子の形態で静かに存在している。熱にはかなり強く、大量の食品中、あるいは真空包装など空気と遮断した状態で加熱すると、加熱ショックで目を覚まし
(発芽する) 、温度が30℃~50℃で、とくにタンパク質を多く含んだ食品は猛烈に増殖する。
(さばの煮付け、カレーの残り、さつま揚げ、細切りハム、竹輪、蒲鉾、厚揚げ、ひき肉などが要注意である。)
この菌は酸と塩と酸素に弱い。空気に触れている料理は心配ないが、密封する加工食品では食酢などの酸あるいは食塩またはそれらを併用して増殖を防ぐのが良い。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
27 |
2,144 |
0 |
| 平成 9年 |
23 |
2,378 |
0 |
| 平成10年 |
39 |
3,387 |
0 |
| 平成11年 |
22 |
1,517 |
0 |
| 平成12年 |
31 |
1,776 |
0 |
| ④ エルシニア菌 (Yersinia enterocokitica) |
|
この菌は食中毒としては少量の菌数でも感染し、食した菌数によって、また被感染者の体力によって10数時間~数日の潜伏期間を経て発病する。敗血症、関節炎、結節性紅班、虫垂炎、会長末端炎など多彩な病状を呈するが、もっとも多く見られるのは、腹痛、発熱、下痢を特徴とする急性胃腸炎である。
この菌は犬、牛、豚、 (特に豚) などの保菌動物から食品に移り感染する。低温に強く、冷蔵庫中でも増殖することができる。毒素は菌体内に作られる一種のタンパク質で、菌体が破壊されると溶出する。
この菌は熱に弱く、加熱殺菌は有効である。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
0 |
0 |
0 |
| 平成 9年 |
3 |
68 |
0 |
| 平成10年 |
1 |
1 |
0 |
| 平成11年 |
2 |
2 |
0 |
| 平成12年 |
1 |
1 |
0 |
| ⑤ カンピロバクター菌 (Campylobacter jejuni, C.coli) |
|
この菌を飲食物を介して多量に摂ると、2~5日間の潜伏期間後、下痢、腹痛、発熱、ときに吐き気、嘔吐、重症時には脱水症状を伴うこともある。しかし一般に予後は良好で、死亡するようなケースはあまりない。食中毒菌としての認定は比較的新しいが、世界中で広く発生しており、日本においても幼少児の胃腸炎としてもっとも頻度が高い。
この菌の感染源としては、犬、鶏、豚などの身近な動物や家畜があげられる。また、酸素濃度が5~15%という中途半端のところでしか増殖しない微好気性菌である。
この菌は熱には弱いが、中には食塩3%程度でも増殖するものがいる。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
65 |
1,557 |
0 |
| 平成 9年 |
257 |
2,648 |
0 |
| 平成10年 |
553 |
2,114 |
0 |
| 平成11年 |
493 |
1,802 |
0 |
| 平成12年 |
454 |
1,747 |
0 |
| ⑥ 病原性大腸菌 (pathogenic Escherichia coli) |
|
この腸炎起病性の大腸菌は発症機序のことなる4タイプがあり、それぞれ発病に至る過程や症状は様々であるが主な特徴は次の通り。
|
| 病原血清型大腸菌 |
(EPEC) |
: 腹痛、下痢を主徴とする急性胃腸炎 |
| 組織浸入型大腸菌 |
(EIEC) |
: 赤痢とそっくりの重い症状を呈する |
| 毒素原性大腸菌 |
(ETEC) |
: コレラとよく似た水様性下痢症 |
| 腸管出血性大腸菌 |
(EHEC) |
: 出血性下痢を伴う大腸炎 |
| これらの菌は熱、塩分、乾燥に弱いので加工食品の製造ではこれらを組み合わせて考えるとよい。 |
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
179 |
14,488 |
8 |
| 平成 9年 |
176 |
5,407 |
0 |
| 平成10年 |
285 |
3,599 |
3 |
| 平成11年 |
245 |
2,284 |
0 |
| 平成12年 |
210 |
3,155 |
1 |
| ⑦ 黄色ブドウ球菌 (Staphylococcus aureus) |
|
この菌が多量に増殖した食品には毒素 (エンテロトキシン)
が生産され、此れを食すと食後1~6時間で胃腸障害を惹き起こす。症状はまず激しい嘔吐に始まり、半数以上に腹痛、下痢が起こる。通常発熱はない。一般に短時間で治まり死亡する事はほとんどない。
この菌の感染源は人や動物皮膚、粘膜表面など自然界に広く分布している。特に切り傷などで化膿している黄色い膿はこの菌の塊と思っていい。手などに傷のある人は食材に触れる作業から外さなければならない。また、人によってはこの菌が常に検出される、保菌者もいるので、手、鼻、顔の皮膚の拭き取り検査を実施しこのような人は前述製造現場から外さなければならない。
この菌は熱には弱いが、塩分に異常に強く、20%程度の食塩があっても増殖するほどで注意が必要である。毒素は熱に強いため、一度毒素が生産された食材は、加熱殺菌して菌を殺しても毒素が残り食中毒を起こす。加熱すれば大丈夫との考えは
(この場合はもちろん、他にもイロイロあるが)
通用しないので注意。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
44 |
698 |
0 |
| 平成 9年 |
51 |
611 |
0 |
| 平成10年 |
85 |
1,924 |
0 |
| 平成11年 |
67 |
736 |
0 |
| 平成12年 |
86 |
14,665 |
1 |
| ⑧ ボツリヌス菌 (Clostridium botulinum) |
|
この菌が食品中で繁殖すると極めて毒性の強い毒素を生産し、その食品を摂ると12時間~24時間、早いものは2~6時間、遅いものは2~3日の潜伏期間後に、吐き気、嘔吐、瞳孔散大、焦点が定まらず、嚥下困難、発語困難などの症状を呈し、さらに呼吸困難、循環器障害を起こし、抗毒素血清の投与が遅れると死亡する。
この菌は土壌中に広く存在し、土物と言われる植物の加工食品製造の場合は要注意である。加熱しても煮沸程度ではその耐熱胞子は死滅せず、かえってヒートショックにより、胞子が芽を出して増殖するスピードを速める。ただし、毒素は蛋白質で熱に弱く、煮沸によって毒性を失う。従って食す前に加熱すれば菌は生き残っても毒性はないので中毒を起こさない。
この菌の特徴は空気 (酸素) があれば増殖できずまた酸にも弱い
(pH6以下では増殖しない。) 従って空気に触れるような包装や酸性の食品は安全である。逆に、加工食品ではカビなどの対策によくやる真空包装や密封容器詰めはこの菌が増殖できる環境である。さらに加熱煮沸殺菌の組み合わせはこの菌に限っては逆効果である。水分活性の高い加工食品にこのような処理をする場合は製品のpHによって、あるいは防腐効果のある成分の添加などによる、この菌への対策は十分考慮する必要がある。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
1 |
1 |
0 |
| 平成 9年 |
2 |
4 |
0 |
| 平成10年 |
1 |
18 |
0 |
| 平成11年 | 3 |
3 |
0 |
| 平成12年 |
0 |
0 |
0 |
| ⑨ セレウス菌 (Bacillus cereus) |
|
この菌が多量に増殖した食品を摂ると、①1~6時間の潜伏期間の後、吐き気や嘔吐を症状とする中毒を起こす。下痢を伴う場合はまれである。原因となる食品は炒飯、ピラフ、茹でたソバなど熱処理をした後、非衛生的に保存されたものが多い。②もう一つの中毒のタイプとして、下痢、腹痛を起こすのがあるが日本では少ない。
いずれも一般に軽症で、予後も良好である。
この菌の胞子は自然界いたるところどこにでも存在している雑菌でもある。この胞子は熱に強く、熱処理して食品の他の菌が死滅している環境で、空気
(酸素) の存在で猛烈に増殖する。中毒の原因はこの菌がつくるエンテロトキシンと言われているが詳しくは判っていない。
|
| 『発生状況』 (厚生労働省資料より) |
|
発生件数 |
患者数 |
死者数 |
| 平成 8年 |
5 |
174 |
0 |
| 平成 9年 |
10 |
89 |
0 |
| 平成10年 |
20 |
704 |
0 |
| 平成11年 |
11 |
59 |
0 |
| 平成12年 |
10 |
86 |
0 |
| 参考文献 |
; |
『衛生試験法・注解』 日本薬学界編
『生物学辞典』 岩波
『DETERMINATIVE BACTERIOLOGY』 BERGEY'S
MANUAL Eighth Edition |
|
|
|
|
|
|
|
| 会社代表ご挨拶 | 会社概要 | リンク | サイトマップ | お問合せ | |
|
|
|
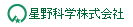 |

